身体拘束適正化のポイント

ご利用者の身体拘束は大変深刻かつ難しい問題です。「身体拘束0」と理想を掲げることは容易ですが、現場では決して拘束したくてしている訳ではなく、「ご利用者の安全のためにせざるを得ない」という切羽詰まった事情があるためです。つまり、身体拘束とリスクマネジメントは表裏一体の関係にあるといえます。
また、虐待防止のページでも解説したように、現状では違法な「身体拘束=身体的虐待」と見做される運用となっているところ、程度を越えた拘束は虐待の問題にもなるというリスクがあります。
皆様も日々、ご利用者の「安全」と「自由」のどちらをとるかというジレンマに悩まされていることと思いますが、本ページをご覧頂くことで対策の方向性が分かり安心頂けることでしょう。本ページでは、身体拘束について事業所が知っておくべき最低限の知識、現場対応の考え方とポイント、現場当事務所がご提供できるメリット等について解説します。
目次
身体拘束に関する基礎知識
身体拘束の定義と範囲
そもそも、身体拘束とは何を指すのでしょうか。ご利用者の行動の自由を奪うもの全般を指すのであれば、施設玄関やエレベーターをロックすることは、みな拘束に該当してしまうのでしょうか。センサーマットはどうでしょうか。
現場で違法な身体拘束を見抜くためにも、何が身体拘束に該当するかを判断するための定義を固めておくことがまずポイントとなります。
身体拘束に関しては、本稿執筆の令和4年時点では虐待防止法のように明確にルールを定めた法律が存在せず、厚生労働省令(運営基準)のレベルで次の条項があるのみです(特養以外も同様)。
指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第11条第4項)
これによると身体拘束の定義は「身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為」となりますが、これでは手がかりになりません。
そこで厚労省のガイドライン「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)をみると、具体例として「徘徊しないように、車いすやいす、ベッド に体幹や四肢をひも等で縛る」「転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る」「点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る」等を列挙していますが、冒頭の玄関ロック等、よく考えると拘束と言い得るようなグレーなケースについて判断指標となる詳細な定義まではしていません。
ですが、現実的に考えて玄関が一般のマンションのようにフリーパスとなっている施設は珍しく、これが拘束と見做され禁止されては施設運営が成り立たなくなってしまいますね。センサーマットも同様であり、結論として身体拘束には該当しないはずです。そのような結論から逆算して定義を導き出すと、次のような定め方になるものと考えます。なおこれは筆者の考えによるものであるため、飽くまで参考にとどめてください。
特定の利用者の行動の自由を直接的に制限する行為
この定義によると、玄関ロックは行動制限に当たるとしても「不特定の」利用者の行動制限なので、身体拘束には該当しないことになります。
「直接的に」とは、物理的に身体を縛る等して拘束する場合、もしくは対象となる行動を制限することを主目的とする場合を指します。目的に関しては、その行為の態様や程度等の諸般の事情を総合的に考慮した上で判断します。
例えばスピーチロック(ご利用者に対し「動かないで!」等と大声を出すことで動きを制限する行為)については、物理的には対象となる利用者の身体に触るものではないため、その点では「直接」制限するものとはいえないかもしれません。しかし、対象となる行動を制限することを主目的としていることが明らかであるため、身体拘束に当たるといえます。
一方、センサーマットについては、マットに着地することでセンサーが発動するだけなので、物理的に直接身体を拘束するものではありません。また、「特定の利用者の行動の自由を結果的に制約する」結果となる可能性はありますが、その主な目的は行動を制限しようとするものではありません。もっとも、センサーが鳴り職員が駆け付けた後に、毎回利用者の体を押さえ付け歩かせないようにしているのであれば、利用者の行動の自由の制限が主目的といえ、センサーマットの「扱い」が身体拘束に該当するといえます。
従ってセンサーマットを設置すること自体は身体拘束には当たらない、という結論になります。
ゼロへの手引き記載の例示があまりに硬直的に運用され、ベッドを壁際に置き、壁以外の三面を柵で囲むことで「四点柵ではないので身体拘束ではない」と言ってみたり、椅子に座ったご利用者を必要以上にテーブルぎりぎりまで押し込み立てないようにするといった「隠れ身体拘束」が散見されます。当たり前のことですが、「書かれていないことはやってよい」という訳ではありません。自分の頭で考え判断することこそが重要なのです。
「特定の利用者の行動の自由を直接的に制限する行為」に当たるか?という視点で今一度現場を見直してみましょう。
身体拘束は一切禁止? ~法律が求めていること~
身体拘束に該当するとして、次に検討することは「例外的に許されるか」というステップです。
実は、法令や行政が施設に求めていることは飽くまで「身体拘束を一切しない」ことではなく、次の通り例外を認めています。行政がしばしば号令として使う「廃止」「拘束ゼロ」という言葉の意味は、「身体拘束ゼロという理想を目指し、できる限り拘束をしないという方針で臨んでほしい」ということにすぎません。
指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第11条第4項)
「当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」は例外的に身体拘束をしてもよく、むしろすべきである場合も十分考えられるのです。次のようなケースを考えてみましょう。
(ケース1 避難訓練時の安全確保)
介護施設で地震を想定した避難訓練を行いました。
お昼に実施しましたが、夜間想定であるため、職員一人が車椅子に乗ったご利用者を二台、交互に押し廊下を素早く移動しました。
一人のご利用者(要介護3)は座位不安定なため、車椅子から落ちそうになり「怖い」と言いましたが、職員は焦りもあり、構わず続けました。
その結果、ご利用者は前傾の状態で転落し顔面を受傷、鼻と顎骨を骨折しました。
家族からは「母は元々不安定だったのに、なぜ安全ベルトをしてくれなかったのですか?」と詰問されました。
施設長は、「いえ、それは身体拘束になってしまうのでできないのです」と答えました。
(ケース2 介助中に別のご利用者が事故)
夜間、施設の居室で車椅子に座ったご利用者(円背、前傾姿勢)のケアをしていた職員。「ドスン」と大きな音が別室から聞こえたので、急いで部屋を出て現場に急行しました。すると、残されたご利用者が前のめりに車椅子から落ち、顔面を強打し大怪我を負ってしまいました。
家族からは「前から、車椅子で一人にするときは安全ベルトをしてくださいと言っていたのに、なぜベルトをしてくれなかったのですか?」と尋ねられました。
施設長は、「安全ベルトは身体拘束になってしまうのでできません」と答えました。
身体拘束を「例外なく禁止」と捉えている職員は、このような杓子定規な対応をしてしまいがちです。しかし、利用者の「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」であれば、少なくともケース1のときは安全確保を優先すべきといえます。
ケース1では、後述する拘束の三要件を満たすといえ、例外的に安全ベルトの使用が許されます。拘束する時間は訓練という特殊な状況下に限定されるところ、「一時性」の要件は満たしており、その他「切迫性」「非代替性」の要件も十分満たすと考えられます。現実的に考えて、利用者の安全を守るための避難訓練が、実施するたびに転倒事故を起こしていては本末転倒ですね。
「そもそも避難訓練の実施方法や計画に問題があった」という問題も無くはないですが、一刻も早く避難すべき状況下では、事前に立てた計画通りいかないことも当然想定されます。職員一人で複数の利用者を同時に避難させなければならない状況も想定すべきといえ、その場合は安全ベルトを現場の判断で付けることもできなければならない、と筆者は考えます。少なくとも、「安全ベルト等の拘束具は一切使わないから、全て処分する」といった極端な排除をする必要はないといえます。
ケース2について言えば、実は施設長の見解は半分正解で、半分間違いといえます。
本件では後述する拘束の三要件のうち「一時性」「切迫性」を満たしますが、「非代替性」の要件が欠けています。例えば当時、この職員はご利用者を急いでベッドに移乗させたり、洗面台などの正面に車椅子を移動させて前傾で床に落ちない状態を作ってからその場を離れること(=代替措置)が可能でした。その意味では、このケースにおいては3要件を満たさない以上「身体拘束は認められない」といえ、その点で正解です。しかし、「安全ベルトはいかなる条件でも禁じ手」と認識していたのであれば、そのような「100か0か」という考え方が間違いなのです。
人員配置基準が4対1に緩和されると、施設内での職員間の連携も更に困難となることが予想されます。人手が手薄な状況下で突発的な事態が起きたときは、やむを得ずそのときだけベルトで固定することも許されるようになってくるかもしれません。元より筆者は、そのように人手不足を理由に非代替性の要件が緩和されることが望ましいと考える訳ではありません。
言いたいことは、「安全確保のため、やむを得ず身体拘束しなければならないとき、拘束が許される場合がある」ということをしっかり理解し、いざ必要なときに正しく判断し実行できるようになることが大切である、ということです。最低限、そのような安全策を選択肢として検討できるようにしておきたいものです。
理想が先走ることによる弊害
拘束を文字通りゼロにしなければならないと頑なに運用することは、却って以下のような弊害をもたらすおそれがあります。
・現場の判断でこっそりor勝手に拘束を行ってしまう(夜間、居室のドアにつっかい棒をかけ利用者を閉じ込め、そのことを報告しない等)。
・「隠れ身体拘束」(食事中に利用者が暴れたとき、とっさに押さえつける等)に気づかず、看過してしまう(人権意識の鈍麻)。
・「見た目に明らかな物理的拘束さえ無ければ良い」と考え、薬漬けにしてしまう。
これは「ドラッグロック」といい、厚生労働省の作成したガイドライン「身体拘束0への手引き」にも身体拘束の例として挙げられています(「行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる」)。ところが、肝心の「いかなる場合に「過剰に」服用させたと認定すべきか」がはっきりと示されていないのです。「医師の処方があり、その服用量を守りさえすれば過剰とはいえない」というのが現在の厚労省の見解ですが、これには大きな疑義があります。少なくとも、学会の発出した薬物療法に関するガイドライン等を基準とすべきと考えます。
身体拘束の可否の判断基準
では、いかなる場合に身体拘束が例外的に認められるのでしょうか。裏返せば、どのようなときに「このような拘束は、例え安全目的であろうとやってはいけない」と判断すべきでしょうか。
先に掲載した運営基準によれば「当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」ということですが、「ゼロへの手引き」によれば以下の3つの要件に整理されます。この3要件が最重要ですので、現場職員の方はぜひ頭に入れておきましょう。

1.切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
2.非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
3.一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
以下、事例に沿って考えてみましょう。
事例.チューブを自己抜去してしまうご利用者
ご利用者が体に取り付けられた胃ろうなどのチューブを嫌がり抜いてしまうとして、これを防止するため両手にミトンを装着することは許されるでしょうか。
まず「切迫性」については、チューブを抜去すると生命にかかわるということであればこの要件は満たすといえそうです。
次に「非代替性」ですが、チューブの位置をずらしご利用者から見えないようにしたり、不快感を和らげるといった工夫をすることで抜こうとする行為がおさまるのであれば、そうすべきです。腹巻きのようなベルトを腹部に巻くことで、チューブに触れないようにできるかもしれません。そうした工夫も無効ということであれば、他に代替可能性がないということでこの要件もクリアしたといえます。
最後に「一時性」ですが、一瞬でもミトンを外すとチューブを抜いてしまうおそれがあるのであれば、24時間365日付けていなければならないということになりかねません。それでは一時的といえず、この要件を満たさずアウトということになります。
しかし、終末期にあるご利用者や医療依存度の高い方を優先的に受け入れるような施設では、命に関わることであり背に腹は代えられない…ということもあるかもしれません。人権保障の観点からは望ましいことではないのですが、もしやむを得ず、例えば入所後1週間は混乱や興奮が激しいのでミトンをして様子をみるといった場合には、都度、「職員が見守ることができる午後のこの時間帯は拘束を解除する」といったこのケースでは一時的にでもミトンを外すことは難しいかもしれません。ですが、職員が見守ることのできる時間帯を見つけその間だけは拘束を解除する等、少しでも解除できないかという方向で検討していくことが重要です。
現場で最も落としやすいポイント・記録
 こうした要件の検討と同じくらい、重要なことが「記録」です。運営基準は次の通り求めています。
こうした要件の検討と同じくらい、重要なことが「記録」です。運営基準は次の通り求めています。
指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第11条第5項)
やむを得ず身体拘束を実施する場合は、その分慎重かつ詳細に記録を付けていきます。検討委員会の議事録、日々の拘束実施に関する記録、アセスメントの結果等を、三要件を意識しながら定期的に記録しますが、最も落としやすいのは「入所者の心身の状況」という要件です。省令にこのように書かれている以上、オーダーとして記録に必ず盛り込むようにしましょう。
また拘束は、導入する段階は慎重ですが、解除する際に検討がおろそかになりがちです。一時性の要件で検討したように、少しでも拘束を減らすことができないか常に模索し続けることが大切ですが、拘束を解除することで当然のことですが転倒等のリスクは高まります。良かれと思って解除したところ、その時間帯に転倒してしまい、ご家族から「なぜ勝手に解除したのか」と責任追及されてしまった…というケースもありました。
身体拘束はただ解除すれば良いというわけではなく、必ず表裏一体のテーマであるリスクマネジメントの要素も睨みつつ検討し、ご家族と都度連携するようにしましょう。
身体拘束の適性化の取り組み
平成30年度の介護報酬改定の際、身体拘束廃止未実施減算が改定されました。介護施設(介護保険施設、特定入所者生活介護、グループホーム等)では身体拘束廃止に向けた以下の取り組みが義務化されており、これら4つのうち一つでも実施しないと、利用者全員について所定単位数から1日あたり10パーセントの報酬減算となります。
1 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
2 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
3 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
4 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に(年2回以上、及び新規採用時)に実施すること
指針に関する概要
これは、恐らく殆どの施設において既に整備されていることと思います。念の為盛り込むべき項目を列挙しておきます。
① 施設(事業所)における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
② 身体拘束廃止委員会その他施設(事業所)内の組織に関する事項
③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
⑥ 入所者(入居者・利用者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束の記録
前述したとおりですが、介護日誌等と違い雛形や記載例があまり出回っておらず、実際にどのような書式を用い、何をどこまで書けば良いかセオリーが確立していない施設も多いかもしれません。そのようなニーズに、弁護士法人おかげさまは対応できます。
当事務所のサポート内容
弁護士法人おかげさまは、介護福祉の現場トラブル解決に特化した法律事務所として、これまで多数の身体拘束事例のご相談を受け、トラブルを解決して参りました。代表の外岡弁護士は顧問先の身体拘束適正化委員会外部委員を務め、また身体拘束に関する著作を多数出版しており、この問題のエキスパートであるといえます。
そのような豊富な経験を基に、現場職員向けの身体拘束に関する内部研修をはじめ、委員会の開催方法や記録の取り方、ご家族への説明方法などについて網羅的にアドバイスし、必要に応じ書式等の雛形をご提供、或いは貴施設にフィットする規定を作成することができます。
未然の問題発生防止に向けた顧問契約
「そもそも身体拘束に当たるのか、当たるとして例外的に許されるのか」については、本稿で解説したように非常に判断が難しい場合もあります。拘束をすれば人権侵害となり、拘束しなければ事故が起きてしまう…そのようなジレンマに立たされたとき、是非外部の相談機関である顧問弁護士サービスをご検討ください。些細なお悩みや疑問でも、大事故に繋がる可能性がある以上は速やかに解決しておくべきです。いつでも弁護士に相談できる環境を整備することで、施設全体が安心して本来の業務に集中できるようになります。





 03-6555-3437
03-6555-3437 ご相談予約フォーム
ご相談予約フォーム







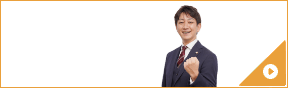


 電話
電話 メールお問合せ
メールお問合せ YouTube
YouTube